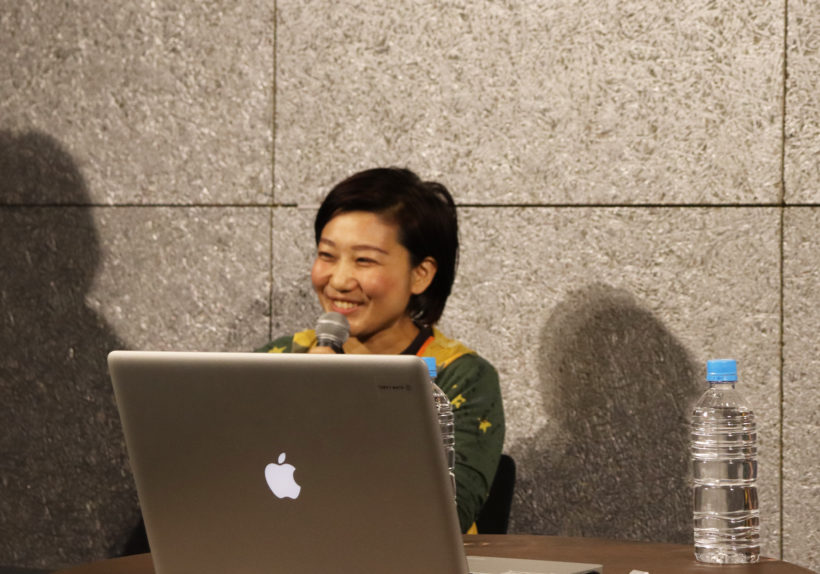インクルーシブなクリエイションの可能性って? “be slow”を合言葉に、アートの力で多様性と調和のある世界をうみだすSLOW LABELさんのイベントレポート!

目次
サーカスを通じて社会をスローに変える「SLOW CIRCUS PROJECT」
 こんにちは。mazecoze研究所のひらばるです。
11月19日に、“OPEN CREATION & TALK SESSION in SHIBUYA:次世代エンターテイメントにおけるダイバーシティ&インクルージョンを考える”というイベントに参加してきました!
このイベントは、NPO法人スローレーベルさんが、“SLOW CIRCUS PROJECT”発足のお披露目をかねて開催したもので、オープンクリエーション、トークセッション、交流会の3部構成でした。
こんにちは。mazecoze研究所のひらばるです。
11月19日に、“OPEN CREATION & TALK SESSION in SHIBUYA:次世代エンターテイメントにおけるダイバーシティ&インクルージョンを考える”というイベントに参加してきました!
このイベントは、NPO法人スローレーベルさんが、“SLOW CIRCUS PROJECT”発足のお披露目をかねて開催したもので、オープンクリエーション、トークセッション、交流会の3部構成でした。

○スローレーベルとは?
国内外で活躍するアーティストとともに、コミュニティがかかえる課題を発掘し、さまざまな分野の専門家や市民・企業・行政をまきこんでマイノリティの視点から社会課題を解決にみちびく取り組みを続けているNPO法人。○SLOW CIRCUS PROJECTとは?
創作活動・人材育成・調査研究・普及活動の4つの事業を軸に、様々な団体や企業と連携しながらサーカスを通じて社会をスローに変えるプロジェクト。

PART1は最後の最後しか間に合わず……
PART1のオープンクリエーションは、「実際の創作現場を見学しながら、必要な配慮・安全管理、専門スタッフの準備や対応などを解説する」というもの。 スローレーベルで活躍する、いろいろな障害や専門スキルがあるアーティストのトレーニング&クリエイション風景を垣間見れる初の試みだったのだそうです。 私は創作活動が終わった頃に駆け込んだので、残念ながら見られずでしたが、会場の渋谷ストリームホールがサーカス仕様になっていて驚きました!クリエイティブで世界を動かす人たちが語る「次世代エンタメにおけるダイバーシティ&インクルージョン」とは?
 PART-2は、SLOW LABELを率いる栗栖良依さん、リアル株式会社代表取締役の小橋賢児さん、一般財団法人渋谷区観光協会代表理事の金山淳吾さんによるトークセッション。
「インクルーシブなクリエイションの可能性、今後の日本のエンターテイメントにおけるアップデートを考える」というテーマについて、多方面で活躍するお3方の対話が繰り広げられました。
何がすごいって、みなさんプランニングやクリエイティブと名がつく形で2020のオリンピックパラリンピックにも関わられていること。
栗栖さんは、東京2020開会式・閉会式4式典総合プランニングチームメンバー。
PART-2は、SLOW LABELを率いる栗栖良依さん、リアル株式会社代表取締役の小橋賢児さん、一般財団法人渋谷区観光協会代表理事の金山淳吾さんによるトークセッション。
「インクルーシブなクリエイションの可能性、今後の日本のエンターテイメントにおけるアップデートを考える」というテーマについて、多方面で活躍するお3方の対話が繰り広げられました。
何がすごいって、みなさんプランニングやクリエイティブと名がつく形で2020のオリンピックパラリンピックにも関わられていること。
栗栖さんは、東京2020開会式・閉会式4式典総合プランニングチームメンバー。

栗栖良依さん
小橋さんは東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会主催の東京2020 NIPPONフェスティバルのクリエイティブディレクター。
小橋賢児さん
金山さんは、渋谷区の観光戦略・事業を牽引し、 2020東京オリンピック・パラリンピック大会ボランティアプロジェクトのチーフクリエイティブオフィサー。
金山淳吾さん
クリエイティブの力で世界と向き合うみなさんから、今回のテーマについてどんな視点をシェアしてもらえるのか? とても楽しみで。 会場には、エンタメ業界の方や、街づくり関係の仕事をする人、障害のある人、ソーシャルワーカーなどなど多様な方々が参加していましたよ!それぞれの視点で捉える「ダイバーシティ」
 トークセッションが始まると、まずは登壇者それぞれの中にある「多様性」というものの感覚を言葉にしていく展開に。
「日本人は良くも悪くも人に気を使って同調圧力の中で育ってきて、本当の自分を見出せていない人が多い。その中で、他人を認めるというのは難しいと僕自身も感じています」と小橋さん。
その上で、多様な生き方、文化がある世界とつながることでリミッターが外れたというご自身の経験をもとに「来年は日本にいながら一気に世界旅行ができるような、多様な文化や多様なイベント、いろんな人と触れ合う絶好の機会」とおっしゃっていました。
トークセッションが始まると、まずは登壇者それぞれの中にある「多様性」というものの感覚を言葉にしていく展開に。
「日本人は良くも悪くも人に気を使って同調圧力の中で育ってきて、本当の自分を見出せていない人が多い。その中で、他人を認めるというのは難しいと僕自身も感じています」と小橋さん。
その上で、多様な生き方、文化がある世界とつながることでリミッターが外れたというご自身の経験をもとに「来年は日本にいながら一気に世界旅行ができるような、多様な文化や多様なイベント、いろんな人と触れ合う絶好の機会」とおっしゃっていました。
 金山さんは、「ダイバーシティについて、同じような意味を持つ言葉でバラエティってあるじゃないですか。なんでバラエティじゃダメで、ダイバーシティって言うんだろうと疑問にも思って自己解釈していった」と、えっと驚く視点から。
そして、「ダイバーシティという言葉は、生物多様性という言葉に起因するんじゃないかと。生き物が死んで養分になって草木が育つというめぐりや、関係性、エネルギーが循環することを、ダイバーシティという言葉で表現しているのではないかと思って。色とりどりなものがバラバラにあるバラエイティとは構造が違って、ダイバーシティには相互性や共有がある」と、おっしゃっていました。おもしろいー。
金山さんは、「ダイバーシティについて、同じような意味を持つ言葉でバラエティってあるじゃないですか。なんでバラエティじゃダメで、ダイバーシティって言うんだろうと疑問にも思って自己解釈していった」と、えっと驚く視点から。
そして、「ダイバーシティという言葉は、生物多様性という言葉に起因するんじゃないかと。生き物が死んで養分になって草木が育つというめぐりや、関係性、エネルギーが循環することを、ダイバーシティという言葉で表現しているのではないかと思って。色とりどりなものがバラバラにあるバラエイティとは構造が違って、ダイバーシティには相互性や共有がある」と、おっしゃっていました。おもしろいー。
エンタメをアップデートするのは、新たなエコシステムと感情報酬!?
 「多様であることには力がある」ということを共有した上で、お次はインクルーシブなクリエイションのためには何が必要か、について。
なるほどーと思ったことや心に残った言葉をご紹介します。
○一歩を踏み出すコツは、専門人材の存在
スローレーベルにはアクセスコーディネーターという、障害のある人が参加するための環境を整える役割の人がいて、「そうした専門人材がクッションとなり、障害がある人はもとより、関わる全ての人が一歩を踏み出しやすくなっている」、と栗栖さん。
障害のある人にとっては様々な配慮があることが伝わると、安心材料になり、そこから口コミで活動や参加者の輪が広がっていくことも多いのだそう。
アクセスコーディネーターは、コミュニケーションを大切にしていて、本人との信頼関係を基盤にして、周りの人からも理解を得ていることから、「創作現場では、心配されることがあったり、本人たちが気にしてしまうから親御さんは入れない(笑)」ことなんかもスムーズに行われているそうです。
多様な人が心身ともに安心して参加できる環境づくりに力を注ぐことが、クリエイションを生み出す基盤になるのですね。
○寄付を通じた新しいエコシステムが大きな原動力になる!?
表現活動の中身だけでなく、持続的に新しいものを生み出すために必要な「お金」についてもお話がありました。
「多様であることには力がある」ということを共有した上で、お次はインクルーシブなクリエイションのためには何が必要か、について。
なるほどーと思ったことや心に残った言葉をご紹介します。
○一歩を踏み出すコツは、専門人材の存在
スローレーベルにはアクセスコーディネーターという、障害のある人が参加するための環境を整える役割の人がいて、「そうした専門人材がクッションとなり、障害がある人はもとより、関わる全ての人が一歩を踏み出しやすくなっている」、と栗栖さん。
障害のある人にとっては様々な配慮があることが伝わると、安心材料になり、そこから口コミで活動や参加者の輪が広がっていくことも多いのだそう。
アクセスコーディネーターは、コミュニケーションを大切にしていて、本人との信頼関係を基盤にして、周りの人からも理解を得ていることから、「創作現場では、心配されることがあったり、本人たちが気にしてしまうから親御さんは入れない(笑)」ことなんかもスムーズに行われているそうです。
多様な人が心身ともに安心して参加できる環境づくりに力を注ぐことが、クリエイションを生み出す基盤になるのですね。
○寄付を通じた新しいエコシステムが大きな原動力になる!?
表現活動の中身だけでなく、持続的に新しいものを生み出すために必要な「お金」についてもお話がありました。
 障害がある人たちも含めた創作活動の集積地と言われて、100%寄付によって成り立っているサンフランシスコのとあるアートセンターについて教えてくれた金山さんが、「日本では、投資という形はあるが、社会をもっと豊かにする活動に対する寄付の流れができればいいのではないか?」と提言すると。
小橋さん「日本では興行になると、チケット収入の枠組みの中で新しい仕組みを作ろうとしても苦しくなり、結果、おもしろみのないものができて、お客さんも楽しめないこともある。新しいエンタメのためには、新しいエコシステムができてこないといけないと思っていて、エンタメの領域が変わっていく中で、いい仕組みが組み込まれて、これまでにない創造性が生み出されていくといいなと思います」
さらに小橋さんが「日本の富裕層の人たちがチームをつくって、パトロンになるっていう(笑)」と言うと、すかさず「2021年以降のテーマは富の再分配だと思っています!」と栗栖さん。
とても、盛り上がっていました。みなさん様々な活動の中で、お金のことも苦労されながら進めてきているんですね。
小橋さん「いまは、時代を変えようとしている人たちが苦しんじゃう。多様な人を入れれば入れるほど、ケアの部分でも大変になり疲弊して、続かない。そこをサポートして欲しいですね」
栗栖さん「文化の活動は、芸術的な作品を作るというだけではなくて、医療でも福祉でも教育でも解決できないところに何か届くとか、変えるきっかけを作るというのがあります。娯楽ではなく意味のあるアクションにつながるので、寄付をしてくださる企業さんが増えると社会が変わっていくなぁと思います」
○日本のエンターテイメントをアップデートするために必要なこと
エンタメそのものについても、いろんな見方でお話されていましたよ。
金山さんが「エンタメは過剰な感情刺激を受けて興奮したり、非日常を体験するもの。(ダイバーシティ&インクルージョンの領域でも)いまのエンタメにはないものを考えて、そうでない感情報酬を打ち出していかなくてはいけないのではないかと」と言うと、「見る人の物差しが一つだと、それでは勝負できない。そうではないところにおもしろさを作らないといけない。それは、障害者が頑張っているというのではないおもしろさ。自分たちだけではできないので、業界の人たちとうまくコラボレーションしていきたいと思う」と栗栖さんが続けます。
「ブルーオーシャンのパフォーマンスを作っていくと、オンリーワンのものが生まれる。そういうものが作っていけたらいいね。組み合わせというのもあると思って、そこは小橋さんがやられていることもそうだと思う」と、さらに金山さん。
障害がある人たちも含めた創作活動の集積地と言われて、100%寄付によって成り立っているサンフランシスコのとあるアートセンターについて教えてくれた金山さんが、「日本では、投資という形はあるが、社会をもっと豊かにする活動に対する寄付の流れができればいいのではないか?」と提言すると。
小橋さん「日本では興行になると、チケット収入の枠組みの中で新しい仕組みを作ろうとしても苦しくなり、結果、おもしろみのないものができて、お客さんも楽しめないこともある。新しいエンタメのためには、新しいエコシステムができてこないといけないと思っていて、エンタメの領域が変わっていく中で、いい仕組みが組み込まれて、これまでにない創造性が生み出されていくといいなと思います」
さらに小橋さんが「日本の富裕層の人たちがチームをつくって、パトロンになるっていう(笑)」と言うと、すかさず「2021年以降のテーマは富の再分配だと思っています!」と栗栖さん。
とても、盛り上がっていました。みなさん様々な活動の中で、お金のことも苦労されながら進めてきているんですね。
小橋さん「いまは、時代を変えようとしている人たちが苦しんじゃう。多様な人を入れれば入れるほど、ケアの部分でも大変になり疲弊して、続かない。そこをサポートして欲しいですね」
栗栖さん「文化の活動は、芸術的な作品を作るというだけではなくて、医療でも福祉でも教育でも解決できないところに何か届くとか、変えるきっかけを作るというのがあります。娯楽ではなく意味のあるアクションにつながるので、寄付をしてくださる企業さんが増えると社会が変わっていくなぁと思います」
○日本のエンターテイメントをアップデートするために必要なこと
エンタメそのものについても、いろんな見方でお話されていましたよ。
金山さんが「エンタメは過剰な感情刺激を受けて興奮したり、非日常を体験するもの。(ダイバーシティ&インクルージョンの領域でも)いまのエンタメにはないものを考えて、そうでない感情報酬を打ち出していかなくてはいけないのではないかと」と言うと、「見る人の物差しが一つだと、それでは勝負できない。そうではないところにおもしろさを作らないといけない。それは、障害者が頑張っているというのではないおもしろさ。自分たちだけではできないので、業界の人たちとうまくコラボレーションしていきたいと思う」と栗栖さんが続けます。
「ブルーオーシャンのパフォーマンスを作っていくと、オンリーワンのものが生まれる。そういうものが作っていけたらいいね。組み合わせというのもあると思って、そこは小橋さんがやられていることもそうだと思う」と、さらに金山さん。
 小橋さん「僕がULTRA JAPANというイベントで花火を上げた時、花火師さんと出会って新しい可能性を感じた。同時に違和感を感じたのが、世の中では伝統を守ろうといわれるが、伝統ってただ守るのでいいのか、ということ。
伝統になる所以には、その時代の人たちがものすごいクリエイションでイノベイティブなことをしたから、その時代の人たちがものすごく感動して、後世に残して伝統になった。情報も多様でコンテンツも細分化するいま、ただ伝統を守りなさいという押し付けではなく、この時代の才能やテクノロジーを組み合わせてアップデートしていかなくてはならない。それをしていくことで、結果的に掘り下げて、伝統を守っていくものとも繋がると思う。
ダイバーシティの分野は日本では始まったばかり。2020のきっかけもある中で、色々な人たちが、栗栖さんの活動などをきっかけに始まっていくというのが、これからの5年10年ではないかと思っています」
ダイバーシティからこれまでにない感情報酬生み出すことや、伝統と革新にまで話が広がっていましたよ。とても勉強になります。
小橋さん「僕がULTRA JAPANというイベントで花火を上げた時、花火師さんと出会って新しい可能性を感じた。同時に違和感を感じたのが、世の中では伝統を守ろうといわれるが、伝統ってただ守るのでいいのか、ということ。
伝統になる所以には、その時代の人たちがものすごいクリエイションでイノベイティブなことをしたから、その時代の人たちがものすごく感動して、後世に残して伝統になった。情報も多様でコンテンツも細分化するいま、ただ伝統を守りなさいという押し付けではなく、この時代の才能やテクノロジーを組み合わせてアップデートしていかなくてはならない。それをしていくことで、結果的に掘り下げて、伝統を守っていくものとも繋がると思う。
ダイバーシティの分野は日本では始まったばかり。2020のきっかけもある中で、色々な人たちが、栗栖さんの活動などをきっかけに始まっていくというのが、これからの5年10年ではないかと思っています」
ダイバーシティからこれまでにない感情報酬生み出すことや、伝統と革新にまで話が広がっていましたよ。とても勉強になります。
オリパラをきっかけに、大きな一歩を踏み出したい
 トークセッション全体を通して、みなさんからひしひしと、2020を一つの機会に世界を一歩大きく変えたい!という意欲が伝わってきました。最後にそのコメントを一部ご紹介します!
小橋さん「多様な人たちをテーマに話すと、本当だったらもっと突っ込みたいところが、気を使いすぎて触れない、喋らないということがある。そうすると行動が起こらない。もちろん相手の立場に立って考えることはとても大事だけど、色んな人たちと絡んでいく中で、失敗もしていかないと。
これからいろんなイベントが様々な文脈で、多方面から。障害だけではなく多様な文化に触れる絶好のチャンスだと思います」
金山さん「ここにいる人たちがこのあと出会いながら、意見交換したり、気のおけない関係になることもはじまりですよね」
栗栖さん「2020年は良い実験の機会。大きな舞台でどうやって効率よく、コストをかけずに、でも皆がハッピーな形でダイバーシティを表現することができるのか。こうすれば良いというのはないので、一緒に考えませんか?というスタンスです。
障害者を起用しなければいけない、というのではなくて、多様な人とやったほうがより強いビジュアルがつくれるとか、よりおもしろいショーが作れる。同じ人が10人よりも、バラバラの人10人の方が、掛け算した時に無限の可能性が生まれる、と知ってもらった時に、初めてやろうと思ってもらえると思うから。このオリパラを通じて、最初の一歩が踏み出せる人が山ほどいるんじゃないかなと思います」
トークセッション全体を通して、みなさんからひしひしと、2020を一つの機会に世界を一歩大きく変えたい!という意欲が伝わってきました。最後にそのコメントを一部ご紹介します!
小橋さん「多様な人たちをテーマに話すと、本当だったらもっと突っ込みたいところが、気を使いすぎて触れない、喋らないということがある。そうすると行動が起こらない。もちろん相手の立場に立って考えることはとても大事だけど、色んな人たちと絡んでいく中で、失敗もしていかないと。
これからいろんなイベントが様々な文脈で、多方面から。障害だけではなく多様な文化に触れる絶好のチャンスだと思います」
金山さん「ここにいる人たちがこのあと出会いながら、意見交換したり、気のおけない関係になることもはじまりですよね」
栗栖さん「2020年は良い実験の機会。大きな舞台でどうやって効率よく、コストをかけずに、でも皆がハッピーな形でダイバーシティを表現することができるのか。こうすれば良いというのはないので、一緒に考えませんか?というスタンスです。
障害者を起用しなければいけない、というのではなくて、多様な人とやったほうがより強いビジュアルがつくれるとか、よりおもしろいショーが作れる。同じ人が10人よりも、バラバラの人10人の方が、掛け算した時に無限の可能性が生まれる、と知ってもらった時に、初めてやろうと思ってもらえると思うから。このオリパラを通じて、最初の一歩が踏み出せる人が山ほどいるんじゃないかなと思います」
 会場に向けてなんども「一緒にやりましょう」「みなさんの力も貸してください」と発していた栗栖さん。この日のイベントを通じても、新たな一歩を踏み出した人がいたら素敵ですね!
ちなみに今回イベントに誘ってくれたWRの森下さんは、「僕、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)に詳しくなかったのに、気づいたらめちゃくちゃD&Iの仕事をしていて!」と言いながら、このイベントの制作運営も担う、エンタメ、クリエイティブ業界ど真ん中の人。
森下さんみたいに、関わりの中でダイバーシティを理解し、一緒に推進してくれる縁の下の力持ちが増えたら、きっともっと日本のエンタメはアップデートするのではないかなと思います。
会場に向けてなんども「一緒にやりましょう」「みなさんの力も貸してください」と発していた栗栖さん。この日のイベントを通じても、新たな一歩を踏み出した人がいたら素敵ですね!
ちなみに今回イベントに誘ってくれたWRの森下さんは、「僕、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)に詳しくなかったのに、気づいたらめちゃくちゃD&Iの仕事をしていて!」と言いながら、このイベントの制作運営も担う、エンタメ、クリエイティブ業界ど真ん中の人。
森下さんみたいに、関わりの中でダイバーシティを理解し、一緒に推進してくれる縁の下の力持ちが増えたら、きっともっと日本のエンタメはアップデートするのではないかなと思います。

SLOW Tシャツが似合っている森下さん。イベントが終了ししみじみ拍手。お疲れ様です!
SLOW LABELさん、ご登壇のみなさま、関係者のみなさま、素敵なイベントをありがとうございました! またいろいろ企画されているそうなので、お話をうかがいにいきたいと思います! SLOW LABEL SLOW CIRCUS PROJECT研究員プロフィール:平原 礼奈
mazecoze研究所代表
編集者・手話通訳士
「ダイバーシティから生まれる価値」をテーマに、企画立案からプロジェクト運営、ファシリテーション、編集・執筆などを行う。
文化芸術、鑑賞サポート、地域、農と食、デフスポーツ、人材開発など様々なテーマのプロジェクトに参画。